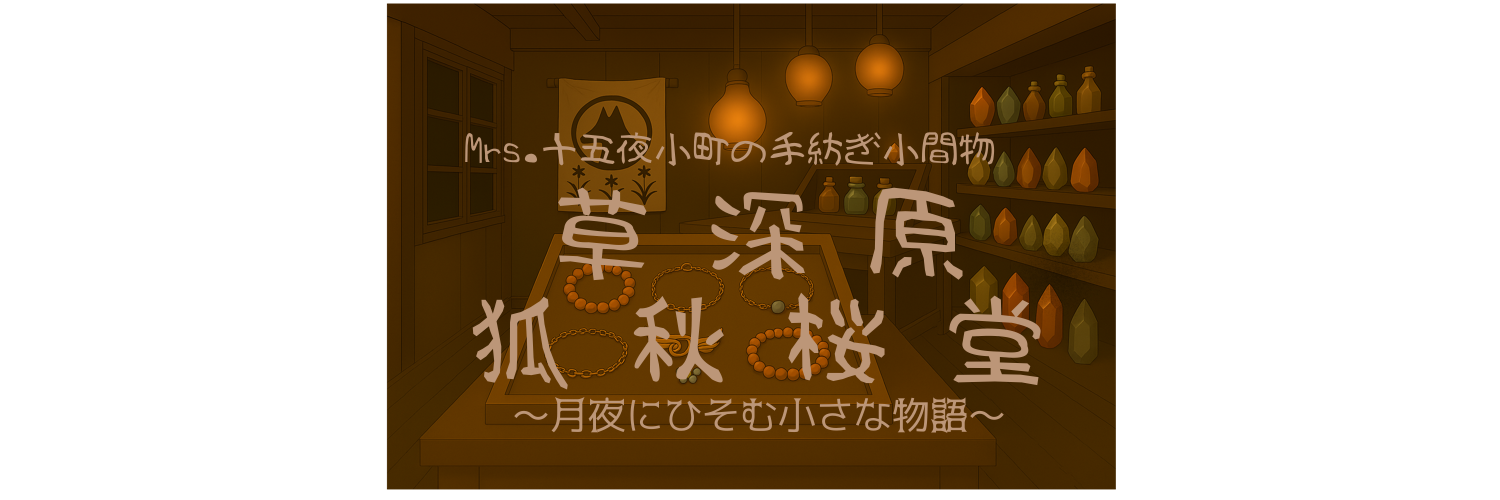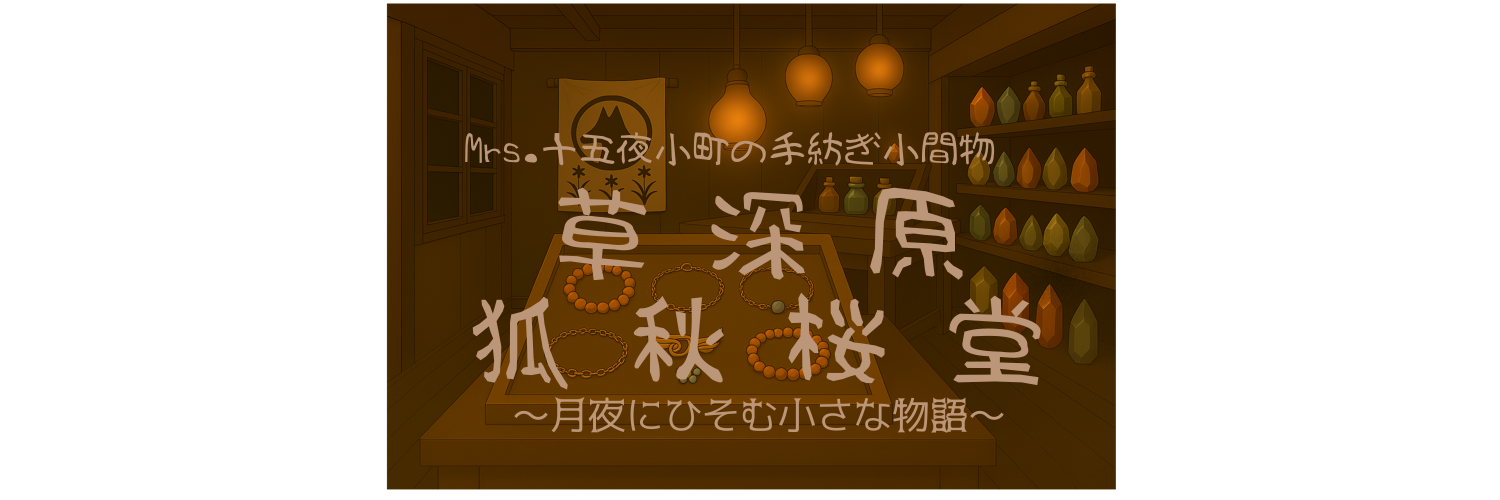2025/07/08 02:09
七月七日、夜の狐秋桜堂。
空には雨の名残が漂い、笹の葉が音もなく揺れていた。
夜杜は、屋根裏から古い紙束を引っ張り出していた。
それは「星譜(せいふ)」――かつて星座を音楽で記すために描かれた五線譜である。
「七夕とはね、天の川の両岸で、“ふたりの旋律”がようやく重なる夜だ。
一年のうち、ほんの数小節だけの合奏。
それも、音程がずれていたらすれ違ってしまう。
だから、誰かが“調律”をしなければならない。
……その役が、ぼくなんだよ。」
夜杜は「星読み飴」をひと粒、缶から取り出した。
金平糖に似た結晶のような飴で、舌の上で星のように弾ける甘さ。
“音になり損ねた願い”の味だという。
彼は笹の短冊を一枚、そっと手に取った。
「願いごとはね、まだ楽譜に書かれていない未来の旋律さ。
今日だけは、それを仮譜として音にしてもいい。」
そう言って、五線譜の余白に、
織姫の主旋律を――弦のようにたゆたいながら、
彦星のバッキングを――低く、けれど真っ直ぐに記していく。
すると、狐秋桜堂の古ピアノが、誰の手もないのにぽろんと鳴った。
♬ポロロン……願いが、音になった瞬間。
夜杜は短冊をそっと五線譜の隙間にしまいながらつぶやく。
「願いとは、“一度きりのセッション”みたいなものだ。
成就しなくても、音になった時点で――それはもう、美しいんだよ」
その夜、狐秋桜堂の上空には、星のように細かな音符たちがまたたいていた。
誰かの願いが、そのなかで旋律になろうとしていたのかもしれない。